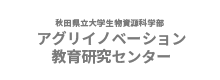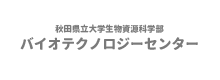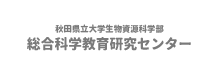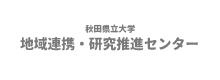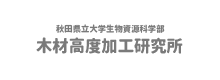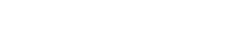調査日:7月22日
1.調査目的
持続的農業について学んでいく中で、生産者だけでなく消費者の理解を図ることが重要であると知った。そこで私たちは、その両者を結ぶ、持続的農業への取り組みを支えている飲食店を対象に調査を行った。飲食店を創業した意図を知り、自然食品や有機農産物を取り扱う上での課題や今後について学び、理解を深める。また、コロナが流行っている中で、飲食店の現状を把握する。
2.店舗の概要
秋田市内にあり、自然食品などの販売とオーガニックにこだわった料理を提供するカフェを併設している。その他には、近隣の飲食店に食材を販売、秋田駅前商業施設内にある店に弁当を卸している。 また、ヨガやライブの会場となる場所を提供(2階飲食スペース)や、月に2回の料理教室(2階飲食スペース、現在は行っていない)などを行っている
表2 お店の基本概要
| 経営形態 | 個人 |
| 労働力 | 経営者、娘、パート |
| 販売品目 | 食品類、生活雑貨、衣料品 |
| 事業形態 | 1階を小売店、2階を飲食店舗 |
3.創業経緯
経営主は、もともと自分の店舗を持ちたいという気持ちがありながら、多様な職業に就いていた。姉から自然食品を勧められ、また当初は自然食品を取り扱う店舗が少なかったこともあり、創業に至った。「身体と地球にやさしいお店」というコンセプトのもと、自然食の良さを伝えることを目標にしている。
表3 創業後の経営展開
| 2003年 | 秋田市山王に1号店を創業 |
| 2006年 | 秋田市役所裏のマンションの一階に移転 |
| 2011年 | 現在の秋田市中通に移転 |
| 2018年 | 2号店を創業 |
| 2020年 | 2号店を閉店 |
4.店舗での販売について
店舗内で販売している農産物の仕入れは、県内の仕入れ先は環境に配慮した農業や持続可能的な農業に取り組んでいる生産者がほとんどである。県外だと京都や北海道から」仕入れている。農産物の仕入れは季節によって仕入れ先の割合が変わってくる。夏季は8~9割が秋田県内から仕入れをしている。冬季は逆に県外からの仕入れが多くなる。
有機農産物のPRは経営主の娘がLINE、Instagram、Facebookを使って発信している。主にLINEを使用している。新規入荷の情報などを発信している。生産者の情報もSNS(主にFacebook)を使って発信している。また、生産者からチラシを置いてほしいという要望が来ることがある。
5.カフェについて
人が集まる場所を提供したいと考えていたため、オープン当初から併設した。当初は3席ほどであったが、徐々に規模を拡大し現在は16席(椅子を入れると20席)でやっている。
メニューは自然食ランチ、玄米チャーハン、ツナとトマトのサラダなどがあり、どれもマクロビオティックにこだわっている。ターゲットは決めていないが、女性は男性よりもマクロビオティックに興味があるため、結果的に女性の利用客が多い状況である。
店舗で扱っている食品のうち、賞味期限が近いものを使うこともあるため、店舗の食品ロスを削減する効果がある。また、カフェのスペースでは料理教室も行っている。参加した方が帰りに野菜を買っていくことが多く、店舗での販売促進につながった。カフェの売上は上昇傾向にある。
6.課題と今後の展望について
店舗での小売における課題としては、店の狭さと駐車場の少なさが挙げられた。店舗面積は1階2階ともに56㎡であり、駐車場は3台までしか置けない。カフェの経営における課題は、マクロビオティックにこだわりすぎているためか、気軽に入れる雰囲気とは言いにくい、ということが挙げられた。また、価格帯を低くすることに対する検討も必要であると考えている。
スウィートマーケットの今後については、健康な生活のお手伝いができるお店にしたいという、創業当初と変わらない思いである。また、お客さんとのつながりを大切にし続けていきたい、品揃えを増やすためにもお店を広くしたいとのことだった。
今後新たに取り組んでいきたいこととして、いくつか挙げられた。1つ目は有機農産物だけでなく、アレルギーにも対応したものを取り扱ってみたいということ。2つ目は、自分自身も農業に挑戦してみたいということ。3つ目は小規模でいいので、食べ物にこだわった老人施設をやってみたいということである。さらに、有機農産物を広げるために、農業体験などの生産者と消費者を結びつけられることをしたいと仰っていた。
7.調査からわかったこと
自然食品の良さについて知り、体にいいものを広めて健康な生活のお手伝いをしたいという思いがあり、お店を始めたということが分かった。店の2階飲食スペースを様々な形で提供することからも分かるとおり、経営主は人が集まることを店を経営する上での大きなコンセプトとしていた。年齢層や性別によって食に対するニーズは様々であり、オーガニック食品を広めるためにはそこに対応する工夫が必要である。
有機農産物やマクロビオティックなど、まだ認知度が低く、大衆向けではないものを扱ってている分、個人経営のような規模で行う方がやりやすいのではないかと考えた。値段が高いことが課題であると仰っていたが、生産費が高いことや、流通コストが高いことが要因として挙げられると思った。小口で流通されることが多いため、農協と比べると農産物一つ当たりの値段が高くなる。
また、個人経営の店舗に対して資金的な面での援助が必要であると感じた。そのためにも、店側が支援を受けられる理屈を持っているなど、援助を受けるための仕組みを整えていくことが必要である。経営において、意識が高くても続けられなくなる人がいる。そういった面を補う何かが必要であると考える。この理念がみんなのためになるのかがはっきりしないと制度の対象とはならない。