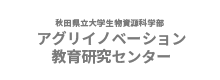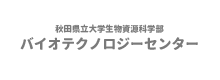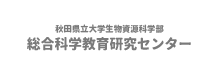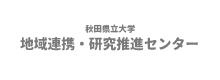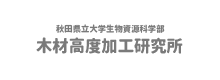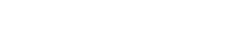こんにちは。最近、めっきり寒くなってしまいましたね。私は、晴天の下にある木の、枯れている姿が、どこか寂しげな感じがして風情のある景色だな、と思いながら過ごしています。また、私は寮に住んでいるのですが、どうも暖房の効きが悪くて困っています。もしかして妖怪のせいでしょうか?このように、なんでも妖怪のせいにしてしまう私が一番の妖怪なのかもしれませんね。気をつけます。
今回は、地域ビジネス革新プロジェクトの良い点について書いていこうかなと思います。
今年の2年生は、あまり地域ビジネス革新プロジェクトに興味が無いようなことを、教授やゼミのメンバーに聞きました。私は特に落胆するなどはしなかったのですが、ある教授は少し気になっているようでした。私たちと一緒に秋田県立大学を去る身なのに、そんなに気に病むことかな?とは思いましたが、なにかあるのでしょうか。もしかしたら劣等感なんかがあるのかもしれませんね。
本題に入ろうと思います。まず、将来は専業、もしくは兼業農家になりたい人には、このゼミ、お勧めできます。さらに言ってしまえば、農家になるならこのプロジェクトに入るべきだと思います。(※私の見解です。)また、農家目線で仕事をしなければいけない職(JAなど)に、就こうと考えている人にも、かなりお勧めできるプロジェクトであると思っています。というのも、このプロジェクトは、農家やJA等の組織へ調査に行き、農業の現状や、農家の経営について深く知ることが出来るからです。ここで重要なのは、調査をすることで、①自分の知らなかった経営のあり方やその内情を知ること②農家の視点や組織の視点を得られることが出来る、という2点です。
①について、農業をおこなう上で、経営というのは大事な要素になってきます。このプロジェクトではそれを知ることが出来ます。机上の論理ではない、実際の経営を農家から直に聞ける機会はそうそう無いのではないかと思います。社会人になってから聞こうと思っても、なかなか聞けないし、教えてくれないのではないでしょうか?また、その経営の良いところを自分の経営に反映することも出来ます。農業をする上で、これを知っているというのは、なかなかアドバンテージがあると思いませんか?私は思います。
②について、農家の見ているものと組織の見ているものは、意外と違います。農家や組織に、何のためにこれをするのか、または促進するような事業を展開しているのか、という問いをするとまったく違う答えがかえってくることがあります。今年の調査でもそれはありました。JAをはじめとする組織にとって、この違いは農家との間に大きく溝を作る要因となるため、組織は細心の注意を払うはずです。そのときには、このプロジェクトで培った農家の目線がとても役に立つのではないでしょうか?
今回も長くなりました。見てくださった方、ありがとうございます。何度も書いてはいますが、ここで書かれていることは、私の見解であるため、絶対鵜呑みにしないでください。そうなのか、程度でよろしくお願いします。ただ、正直に自分の思ったことを書いているので、その点に関しては保障できます。
12月11日には、また2年生が来訪します。多くの人が来てくれることを願いますが、どうなるでしょうか?楽しみに待っています。次回の更新は多分無いですが、後期のまとめは掲載すると思います。そちらに関しては、興味のある方が見てくれると嬉しいです。
それでは、アディオス。