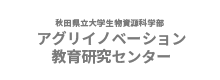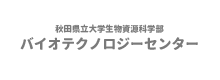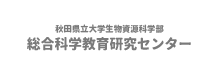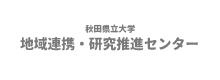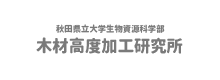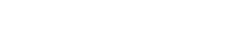今日は、学会のシンポジウムに出席しました。
そこで、先進的な農業経営について議論されたのですが、生産物の出荷先が農協であることは、経営体として不完全であるとか、資本の論理が貫徹されていないとかいうことを示しているのだと言う先生がおられました。その理由を理論的にいうと、生産物を販売するというのは経営体として極めて重要であるから、それを自分でやらないというのは、不完全だということらしいです。
私はこのような話を始めて聞きましたが、ちょっと疑問に思いました。
例えば、製造業の会社が製品の販売部門を独立させて子会社にしたからといって、人任せにしているとか、経営体として不完全になったとは言わないと思います。農協の販売事業は、複数の農家が協同して販売部門を独立させたものだと私は考えているので、この製造業の販売子会社の例とそんなにかわらないように思います。
理論的な世界でなくて、現実として農協の販売事業の成績がイマイチなとき、それでも漫然と農協に出荷を続けるということであれば、それは企業の論理が貫徹していないといってもおかしくはないと思います。
私がこのように考える背景には、取引費用の概念を応用した流通チャネル論があるかもしれません。この議論では、企業は自分の製品の特質を反映した流通を実現させることと、それに要する費用を低く抑えることを両立させるという問題が論じられています。そして、流通を他の業者に任せるか、自らおこなうかは製品の特質によって影響されるとしています。
このように、流通チャネル論を知っていれば、自分で売るかどうかはケースバイケースであるという感覚を持つことでしょう。つまり、販売を誰かに任せた方が高い収益をあげられるケースは、そこまで稀なものではないということです。したがって重要なのは、収益性を最大に高めるという観点で販売方法を選択しているかであって、その結果として農協に販売することになったのであれば、経営体として不完全であるとはいえないと思うわけです。
ただし、取引費用論による流通チャネル論については、私は賛成できない部分もあります。よろしければ、下記リンクの論文をご覧ください。