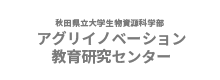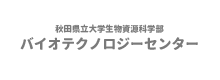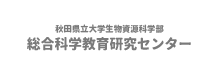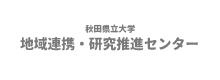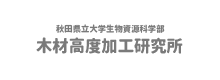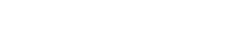いつも、奥さんからあんたの話はクドクド長いねって言われます。自分でもそう思います。あと、そんなに難しいこと考えてるわけでないわりに、無駄に理屈っぽい。今日は、そのような私の個性全開で行きます(笑)。
わが国の農業経営にも企業的な経営が増えているようですが、これは基本的には望ましいことですから、その傾向がますます強まることが期待されます。これに関して問題となるのが、農業経営が「企業的」ってどういうこと?という疑問で、学会のシンポジウムでも取りあげられてきたテーマです。
最近、農業ではなく一般経営学の論文で、ファミリービジネスに関するものを読んだのですが、「ファミリネス」というのが1つのキーワードになっていました。ファミリネスというのは、家族が経営に関わることで経営にもたらされるもので、おもしろいことにこのファミリネスは「資源」なのですよね。創業家の理念などが競争優位の源泉となるという考え方のようです。
農業においては、「企業的」な経営を確立するということを、即座に「家族的」な経営からの脱却と受け止める向きがあるのと、対照的だと思います。この違いはどこから来るかというと、農業でいう「企業的」というのは、人をたくさん雇っているとか、事業の規模が大きいとかいう経営の外形的特徴を指す側面が強いのに対し、ファミリネスの議論は、所有と経営が一致しているか分離しているかに注目するところにあると思います。一般経営学が対象にする企業は、中小企業を考えたとしても、通常はすでに人をたくさん雇ってある程度の規模があるわけですから、人を雇っているかどうかを問題にする意味はあまりないのでしょう。そのかわりファミリネスの議論では、創業家やオーナー経営者の支配が強い企業に注目しています。そのような企業は、株主とは別に雇われ社長がいるような企業と比べて、所有と経営が一致しているというわけです。
オーナーとその家族が直接経営にたずさわると、例えば短期的な利益を求める株主の要求に左右されないので長期的視野を持った経営が出来るとか、そういったファミリネスを持つ企業に特有の行動様式が生じるという視点が、一般経営学におけるファミリービジネスの研究ではみられるようです。もちろん、一族の資産価値を損じるのを嫌ってリスクを取らないとか、必ずしもファミリネスがプラスに働くとは限らないのですが。
こうして考えると、農業経営についても、ファミリネスの意味でのファミリー性が高いことと、規模が大きいとか人をたくさん雇っているとかいう外形的な企業的特徴とは、独立した軸で捉える方がよいように思います。つまり、家族的な農業経営の反対が企業的な農業経営と考えるのではなくて、家族的でありかつ企業的である経営もあるというように考える方がよいのではないかということです。
ついでにいうと、企業的な農業経営を論じる人の多くが興味があるのは、その経営がアントレプレナーシップを発揮できるかということだと思います。アントレプレナーシップとは、イノベーションに取り組んでいる活性度と考えてください(企業家精神と訳するのは、あまりよくないと思います、企業家活動と訳すべきです)。人をたくさん雇う企業であっても、イノベーションはあまりやっていないという経営は考えられます。したがって、農業経営の性質(企業形態的特質とでもいうのでしょうか)は、ファミリネスが発揮される度合い、アントレプレナーシップが発揮される度合い、企業的な外形的な企業的特徴を備えている度合いの3つの軸で捉えるのがよいと思います。これらの軸は、お互いに影響を及ぼしたり制約条件になったりしながらも、別々の性質なのだと考えるのがよいのではないかと考えました。
ところで、以前このような話を、お酒を飲みながらしていました。その時は、まだファミリネスのことはよく知らなかったのですが、所有と経営の分離がされているかどうかに注目して議論するのがよいという考えはもっていました。だいぶ酔っていてうまく説明できませんでしたけど。
で、そのとき「人を雇うと、従業員とその家族を失業させてはいけないとか、経営の目的がずいぶん変わってくるものだ」ということを強調する先生がおられました。この先生は、私とは違って、ファミリネスよりも外形的な企業的特徴の方を重視していると思われるわけですが(この方だけではなく、ほとんどの農業経営学者はそうでしょう)、従業員のことを考えて経営するというのは、企業的かどうかとはまた別の論点であるし、さらに言えば、むしろ家族経営的な側面を示すもののように思います。
それは、一般経営学においては、「スチュワードシップ理論」で捉えられるものでありましょう。これは何かというと、性善説を具現化した経営みたいなものです。もう少し詳しくいうと、「組織や社会の目的を達成しようと行動することで個人の効用が最大化され、自己実現につながるため、経営者は企業環境、組織環境を整えて参加型の経営を促す役割を持つ」ということのようです(引用元論文へのリンク)。
このスチュワードシップというのは、ファミリービジネスと相性がよいようで、エージェンシー理論とともに、ファミリービジネス研究で盛んに用いられる理論が、スチュワードシップ理論だそうです。「同族企業にとって、会社とは自分達の夢の実現の手段であり、高いスチュワードシップを発揮する」というような表現が、このことをよくあわらしているといえるでしょう(引用元論文へのリンク)。だいぶ前にCSRということがずいぶん言われたりしましたが、株主利益に配慮しなければならない雇われ社長は、スチュワードシップ的な行動に思い切って踏み込むことは難しいでしょう。なにせ、スチュワードシップ理論において最大化されるのは、金銭的利益ではなく、上の引用文にあるように、「個人の効用」なのですから。このように考えるならば、従業員をたくさん雇うこと自体はともかく、従業員のためを思って経営することは、何か企業的な性質を表すものとはいえないかと思います。