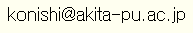経緯をふまえた補足説明を。
「そのとき細胞に」に対するアプローチは、熱力学モデルを得たことで変わるだろう。
現在はその過渡期であって、プロトコールも過渡期のものだ。
ややこしいことに、それぞれ「現在まで」「完成後」「過渡期」でかなり方法が異なる。
まず、ノザンなどで増えた・減ったという画像を得る。そして
それが増えた・減ったことと矛盾をしないストーリーを用意して説明する。
この方法はナイーブで、複数の実験結果を統合しにくい。
標準化がユニバーサルなものでないため、複数の報告間で増減の比較ができない。
また、データが増えると矛盾のないストーリーを用意するのが困難になる。
以上から、網羅的なデータ解析をこの方法で行うのはまず無理だ。
さまざまな刺激の細胞への影響を、因子の活性濃度変化で理解できるようになる。
もちろん、網羅的で客観的に。
できないこと・定数を求めていないので、マイクロアレイで測定した
各遺伝子産物の濃度変化を因子の変化に直ちに還元することはできない。
だから?
できること・遺伝子産物の濃度変化をタイプファイすることができる。
それで?
| Go Back | Home | 解析方法のインデックスへ |