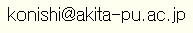学問の諸分野もまた、科学と同様に、定義するのが難しい。
やはり、移ろい行くものだからだ。
それらについて論ずるのは、また困難さがある。
どうかしてその「定義」が揺らいでしまうと、
論じたことの意味合いがおかしくなってしまうからだ。
とはいうものの、ここで分子生物学について論じようとおもう---
生化学と対比させて。
だからそれに先立って言葉を定義しておこう(そのページへ)。
一見すると、これらの定義はとても似ているのだけれど、
よく考えると根本の思想がかなり異なることがわかる。
生化学にはいつも科学的な背骨「化学」がある。
物質が化学反応するための機構は、化学によって明らかになって(きて)いる。
その共通原理をもとに、もっと複雑な現象を説明していこうとする方向性、
単純から複雑へ向かう方向性を、生化学はもっている。
これに比べて、分子生物学は(少なくともそのおこりの段階では)
あまりはっきりした背骨を持っていなかったのではないかと思われる。
なにかを、あるレベルで記述するというのは、むしろ博物学の考え方だ。
収集するためには、形のきまったオリよりも、
もっと融通無碍なしなやかさが有利だ。
検証は後でもできるから。
もちろん、分子生物学的な分野でも、いくつもの法則が発見されてきた。
それらが後付けの背骨として機能してきて(きっと、とても有難かったはずだ)、
いまの分子生物学があるのではないかと思う。
ところがこの10-20年くらい、
またその背骨が不足した状態になってきているのではないか。
背骨がないままで体がふくらむと、いろんな問題がでてくる。
記述が先にいきすぎてしまうと、知見を統合することが困難になる。
すると、どうなるか。研究者が研究している内容が、
お互いの研究にとって無関係になっていく。
その結果、掘り下げられた、しかし応用のきかない研究ばかりが増えていくことになる。
これは悲しむべきことである。
人間の理解力には(たぶん)限りがあるのだから、
その範囲で「法則」を見つけ出し、
得た知見をその法に則り説明するほうがいい。
そうすることによって、その法則を共有する人々との間で、
知見を共有できることになる。
たとえば、そのような例として、
ゲノム研究と、トランスクリプトーム研究について考えてみよう。
ノザン法などで遺伝子の発現レベル変動を測定した論文がいくつかあったとする。
現時点では、これらの知見を統合するのは、えらくたいへんである。
定性的に解釈した内容を、不確かな言語を用いて説明せねばならないからだ。
さて、そうした状況下で、マイクロアレイが出現し、
トランスクリプトーム研究が始まった。
これは博物学の権化のような手法で、
遺伝子の変化を網羅的に測定できることになった。
また、ゲノム研究とは塩基配列を片端から読んでいく作業であるが、
読んだ配列が何をしているのか、
確かなところがわからないままにデータが蓄積していった。
まず間違いなく、ゲノムの塩基配列には、遺伝情報の
ほとんどが記録されている。
そのなかには、どんなタンパク質をつくるかという質的な情報のほかに、
そのタンパク質がいつ・どのくらいつくられるべきかという
量的な情報も含まれているはずだ。
そうした情報は、現時点ではまったくわからない。
コードされている文法がわからないからだ。
ここで試みようとしているのは、
そうした「情報の過飽和」を解消すべく、
必要な法則を用意することだ。
でも法則は一日にして成らない。
論文は、検証が完了していない、仮説以上・法則未満の考えとして
発表していくことになる。このページではその論文を紹介していこうと思う。
まず手始めは、トランスクリプトーム分野のデータを比較可能にすること、
(比較可能なら、それらのデータから得た知見は統合できる)
そしてゲノムの塩基配列とトランスクリプトームとをつなげることだ。
そんなことできるわけないって?
できなきゃウソだ。細胞は、毎日それをやってるんだから。
いささか面倒だけど、しかし確実な方法がひとつある。
あらゆるものを定量化して、既存の単位系に乗せることだ。
| Go Back | home | インデックスページへ |