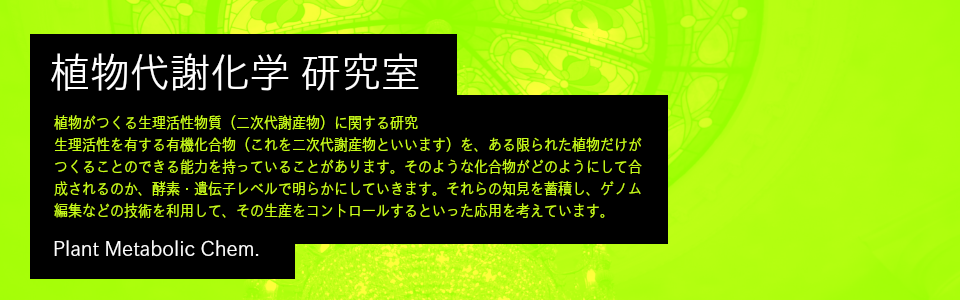植物の二次代謝産物がどのように合成されるのかを明らかにする研究

カフェイン生合成機構の分子進化を探る
当研究室では、カフェインがカフェインシンターゼと名付けられたメチルトランスフェラーゼの働きによって生合成されることを明らかにしました。そのカフェインシンターゼは、植物ホルモンであるインドール酢酸やジベレリンなどのカルボン酸を持つ低分子有機化合物にメチル基を付加(エステル化)する酵素群と、構造的に類似していることがわかっています。
カフェインを持つ代表的な植物としてコーヒーはよく知られていますが、我々が普段飲んでいるコーヒーはほとんどが「アラビカ種」という品種です。じつはそのほかにも様々なカフェイン含量を示す原種が存在します。これらの持つカフェインシンターゼを調べることで、コーヒー(Coffea属)が、どのようにしてカフェイン合成能を獲得し、進化してきたのかを探る研究を進めています。

コーヒーの香り成分蓄積機構を探る
コーヒーの持つ香りはその価値を決める重要なファクターの一つである。香り成分としてテルペン類が挙げられる。低分子テルペン類は揮発性であるため、通常合成とともに空気中に拡散してしまうが、これらを配糖化し蓄積する仕組みを植物は持つ。コーヒーにおけるこの配糖化に関わる酵素遺伝子について調べています。
研究が進めばより香り高いおいしいコーヒーの開発に繋がるかもしれません。

不定根発生に関わる生理活性物質を探す
発根に関する研究は、種子発芽に由来する初期の発根とその後の根系発達の解明が主流でしょう。その一方で、挿し木などで見られるいわゆる不定根発生については不明な点が多いのが現状です。この仕組みを解明できれば、挿し木の難しい希少な植物や果樹などの優良品種の大量増殖を容易にするなど、産業分野への応用も期待されます。
タデ科の植物ミゾソバは水に挿しておくと2、3日で発根が見られます。この挿し穂の不定根発生に際して発現量に変化が見られる遺伝子に注目し、次世代シーケンサーを用いた大規模発現遺伝子解析を進めています。