これは「フレームワークの神話」のなかで、
20世紀の科学哲学者であるカール・ポパーが
within which we are able to think
と紹介している概念である。
ここでは概念だけを定義ごと拝借している。
フレームワークの神話 カール・R. ポパー (著),
ポパー哲学研究会 (翻訳) 未来社 ISBN-13: 978-4624932398
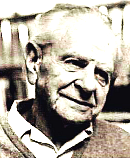 このなかで、ポパーはフレームワークを「必要だけど厄介なもの」
このなかで、ポパーはフレームワークを「必要だけど厄介なもの」
そして「乗り越えるべきもの」と捉えた。
- フレームワークは思考の基盤であり不可欠だ
- 思考の結果はフレームワークに依存する
(だからフレームワーク間の対話は困難だ) - しかし「真理はフレームワークに依存する」わけではない
真理がフレームワークと相互依存するという考え方を相対主義という。
ポパーは、相対主義が科学の進歩を阻害すると考え、繰り返し非難した。
この本に興味を持たれた方へ:
実はこの「フレームワークの神話」は、
データ分析やら科学の仕組みとは趣を異にする本です。
異なる文化(文明)はフレームワークを異にすることが常なので、
文化間の対話はたいへん困難なのだが、稔り多い努力であるからがんばろう、
または、こうした努力なしに平和な未来はない、
という趣旨で書かれています。
 似た概念に、トーマス・クーンが提唱した「パラダイム」がある。
似た概念に、トーマス・クーンが提唱した「パラダイム」がある。
自然科学の分野を扱おうとした試みとして考えると、
パラダイムのほうが、よりふさわしいかもしれない---。
いま、人々が「物の見方」「考え方」について言及するときには
こちらのほうがよく使われる。
ではなぜここでポパーやフレームワークを引用するのか?
パラダイムは便利な言葉だが、あいまいだ
(後にはクーン本人も使わなくなったようだ)。
パラダイムの本来の意味は、「ある時代にお手本となった論文(仕事)」だった。
「その時代になされる仕事は、革新的だったいくつかの仕事の焼き直し(または発展)であって、
次の革新がなされるまではずっとそれが続く」というのがクーンの見方であった。
この第一義は、思考のための前提条件の有機的な集まりとは異なる。
その点、考えるための基盤となっている定義や仮定の集まりと説明する
ポパーのフレームワークは、まさにここで使いたい意味を的確に表すものだった。
科学革命の構造 トーマス・クーン (著), 中山 茂 (翻訳)
みすず書房 ISBN-13: 978-4622016670
お断り:筆者はポパーとクーンの間の論争をテキストで読んだことがないし
同時代人でもない。筆者はもしかしたら彼らの関係を根本的に誤解しているかもしれない。
ポパーはクーンをかなり批判したようであるけれど、
私は、彼らは同じ現象を同じように捉えていたのだろうと思っている。
それをポパーは教条的に、クーンは客観的に、
それぞれ表現したのではないか。
クーンは、現実はこうですと示した。
ポパーは、それじゃイカンじゃないかと怒ってみせた。
(しかし現実は現実として残る。)
クーンが科学革命の構造で述べたのは物理学の進歩の様子だけど、
これは分子生物学にもそっくりあてはまるものと思う。ひりひりした実感として。
たぶん人間の集団がなにかをするときに、普遍的に、
こうした仕組みが現われやすいのだろう。
クーンは相対主義を擁護したのではなくて、
また科学の状況を批判したのでもなくて、
ただ発見した事象を客観的に報告したのだろう。
もちろんこれは重要な発見だった。
事象が存在しても、それを捉える思考のパターンがなければ私たちは知覚できない、
クーンの発見は新しい見方・考え方の提供につながったわけで、
それこそひとつのパラダイムになった。
さてところで、フレームワーク間の対話が難しいのは「フレームワークの神話」でも
繰り返し述べられている。実際のポパーさんは非寛容な態度をとる方だったようで、
なかなかフレームワークを超えることは難しかったのではないかと思われる。
自分の思い込みをいったん捨てなければならない、
捨てた後に何を頼って考えたらいいのかがわからない、
だからフレームワークを超えるのは本当に本当に困難である。
科学の終焉 ジョン ホーガン (著), 竹内 薫 (翻訳)
徳間書店 ISBN-13: 978-4198913984
真理はともかく、研究の結論はフレームワークに依存する。
だから可能な限り妥当なフレームワークに準拠すべきである。
でも、フレームワークの全様を把握するのは簡単ではない、
意識している部分とそうでない部分があるはだから。
できることは、自分の論拠を隅々まで意識すること、
そしてその場しのぎな考え方を注意深く避けることではないか。
そうした日々の努力が、私たちのフレームワークを健全に育てるだろう。
バイオインフォマティクスから分子生物学にも入ってきていることを感じる。
かっこいいacronymがタイトルに使われたり、
社会学・経済学で使われるような汎用性の高いモデルを使用しているのは要注意。
新規なacronymは誰も意味を知らないし、そうでなくても
当業者には通じないことが多い、
でもあえてそうした単語をタイトルにつけるのは、
迂闊なのか、煙にまいてやろうとたくらんでいるからだ。
また汎用性の高いモデルはしばしば、反証可能性に欠ける。
迂闊でした。
では、妥当なフレームワークとはどんなものか? それは 別のページに。