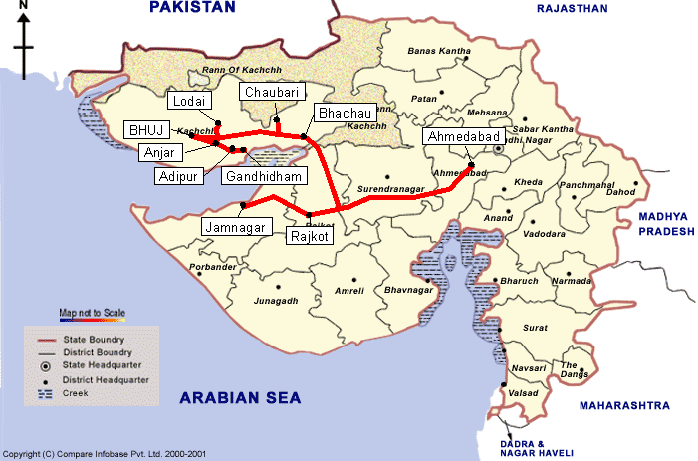
秋田県立大学システム環境システム学科
インド西部地震 被害調査速報
被害調査班メンバー:
Karkee, Madan B 教授 (建築構造力学講座)板垣 直行 講師 (建築材料学講座)
1.はじめに
2001年1月26日にインド西部グジャラート州を震源にM7.9という大変大きな地震が発生し、かつて無いほどの人命が失われ、また建物、その他の社会資本が失われた。この多大な被害を被ったインド国民及びパキスタン国民に哀悼の意をささげると共に、より早い復興をお祈り申し上げる次第である。
この地震による被害情報が、時間の経過と共にその全貌を明らかにするにつれ、その被害がかつて無いほどの状況であることに驚愕させられる思いがしたが、その一方でこのような被害を生み出した地震についての情報はなかなか明らかにされなかった。地震に規模についても、当初の発表のM6.9からM7.9に変更され、震源の位置についても当初発表された位置から修正されるなど、正確な情報がなかなか公表されず、現在でも不明な点も多い。
本学科では、1999年8月のトルコ地震、同年9月の台湾地震について調査を行っており、それらの経験、知識を生かして、今回のインド西部地震における被害の掌握、そしてその原因の究明に僅かながらでも助力出来ると考えられた。また本学科のKarkee, Madan B 教授はインド工科大学の出身であり、インドについて精通しており、ヒンディー語による現地の人々とのコミュニケーションが可能である事など、現地調査の実施に有利な条件があった。これにより2001年2月18日〜25日にかけてインドに渡航し、被害調査を実施することになった。
2.調査旅程
|
日 付 |
スケジュール |
宿泊 |
備考 |
|
|
2/ 18 |
Sun |
移動: 秋田空港7:55−(ANA-872便)→9:00羽田空港 羽田空港10:45−(ANA-143便)→12:00関西空港 関西空港13:10−(NH-955便)→19:25 ムンバイ |
ムンバイ Centaure Airport Hotel Tel.(+91-22) 611-6660 Fax.(+91-22) 611-3535 |
|
|
19 |
Mon |
ムンバイにて情報収集
移動: ムンバイ17:05−(Jet Airways: 9W325便)→18:05アーメダバード |
アーメダバード Holiday Inn Ahmedabad NearNehruBridge, Ahmedabad-380 001. Gujarat Tel. (+91-79) 550-5505 Fax.(+91-79) 550-5501 |
|
|
20 |
Tue |
アーメダバード市街調査、情報収集
|
アーメダバード Taj Residency, Ummed Tel. (+91-79) 286-4444 Fax.(+91-79) 286-4454
|
車をチャーター |
|
21 |
Wed |
ラージ−コート方面調査 5:00ホテル出発 → 9:30ラージコート(RAJKOT)着 ホテルにチェックイン 11:00ホテル出発→13:00ジャンナガ(JAMNAGAR)着 市街・カッチ(Kachchh)湾海岸調査 15:00ジャンナガ発→ 17:00ラージコート着
|
ラージコート Hotel KAVERY Near G.E.B Kanak Road, Rajkot-360 001. Gujarat Tel. (+91-281) 23-9331 Fax. (+91-281) 23-1107 |
アメダバードにて車をチャーター
|
|
22 |
Thu |
ブジ方面調査 4:30ホテル出発 → 7:00マリヤ(Maliya)(以降被害調査をしつつ移動)→バチャウ(Bhachau)→ブジ(Bhuj)→アンジェラ(Anjar)→ガンディダン(Gandhidan) ホテル(ただしテント)にチェックイン
|
ガンディダン Sharma Resorts Nr. Airport Crossing, Galpadar, Gandhidham. Tel. (+91-2836) 3-1823 Fax. (+91-2836) 3-1891 |
|
|
23 |
Fri |
ブジ(震源)方面調査 9:30ホテル出発 →ガンディダン → アンジェラ→12:00ロダイ(Lodai)→14:30(バチャウ)→16:30チョバリ(Chaubari)→17:30(バチャウ)→20:00(ガンディダン)→22:00(バチャウ)→3:30アメダバード
|
Taj Residency, Ummed Tel. (+91-79) 286-4444 Fax.(+91-79) 286-4454
|
チョバリの帰り、バチャウ近郊にてタイヤがバーストし、ガンディダンまでタイヤ購入のため移動。 |
|
24 |
Sat |
アーメダバードにて情報収集
移動: アーメダバード18:35−(Jet Airways: 9W326便)→19:35ムンバイ |
Taj Mahal Hotel
Tel. (+91-22) 202-3366 Fax.(+91-22) 287-2711
|
|
|
25 |
Sun |
ムンバイにて情報収集 移動: ムンバイ20:40−(NH-956便)→(関西空港) |
機中泊 |
|
|
26 |
Mon |
移動: (ムンバイ) −(NH-955便)→7:25関西空港 関西空港8:30−(ANA-142便)→9:45 羽田空港 羽田空港17:50−(ANA-877便)→18:55 秋田空港 |
||
3.調査経路
(http://www.mapsofindia.com/maps/gujarat/h3s1102.htmより地図を転載)
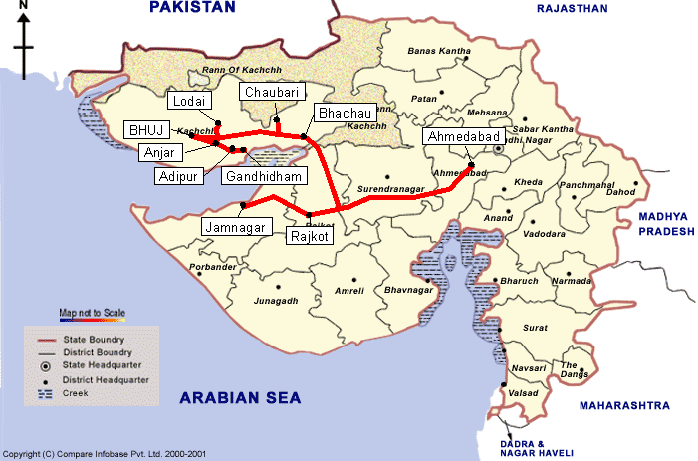
4.調査速報
今回の調査結果についてはまだ十分な解析・検討がなされていないが、新たに調査にあたる方々の足がかりとしていただくためにも、現段階で得られている情報を報告する。今後の検討、また他の研究者の方々による詳細な調査により、修正・訂正などが多々あり得ることをご了承いただきたい。また情報は現地の関係者からのヒアリングによるものが主であり、必ずしも公式な発表に基づくものではないことをお断りしておく。
4-1.アーメダバード(Ahmedabad)
今回の地震によりビルの倒壊などが新聞で報道され、大きな被害を受けたものと考えられたが、実際の被害は、ごく少数の築構造物が著しい(全壊)被害を受けたのみで、その他の建築構造物はわずかな被害で済んでいるようである。
車により市街を巡回中、多少の被害を受けた建築物(いずれも1階が完全にピロティになっているなど、構造的に無理があるようなもの)は見られたが、一部破損程度の被害であり、逆に半壊といったような被害は見られなかった。また空港設備、宿泊したホテル、店舗など、今回の滞在中に訪れた建築物で、地震によるものと思われるクラック等が確認できたのは、わずかであった。市街には中〜高層のビル、マンションなどが多数有り、劣化や根本的な構造計画の問題により地震時に危険と思われる建築構造物も多々見られたが、倒壊の被害を免れている。したがって、今回の地震により倒壊した建築物については、構造的に致命的な問題があったものと考えられる。
現在では都市のインフラ等、震災による影響は全く無いと思われ、交通機関(空港)の利用、宿泊、食事には何の支障も無かった。

写真1 Maninagarのマンション(市街南東部:Maninagar駅そば)
既にほとんど片付けられていたが、左下に見えるようにぐちゃぐちゃに潰れた車が何台か周りに放置されており、1階がピロティとなっていたと考えられる。

写真2 Khokhra Mahmedabadの小学校(市街南東部:Maninagar北、Cadila Helth Care工場向かい)
4階建てであったとの事だが、全壊し35〜40名の生徒が死亡したとの事。

写真3 Maneshi Complex (市街西部)
13階建ての手前側の部分が全壊し、100名程が死亡したとの事。
4-2. ラージコート(Rajkot)
アーメダバードの西約200kmに位置し、ブジからも直線で約150kmの距離に位置する。アーメダバードよりかなり震源に近づいていることから地震の被害が予想されたが、ほとんど被害は見られなかった。現地の人の話では倒壊などを起こした建物は皆無だったようである。車により市街を巡回したが、特に地震の被害らしきものは見当たらなかった。また宿泊したホテルなど、においても、地震によるものと思われるクラック等は確認できなかった。
4-3.ジャンナガー(Jamnagar)
ラージコートにて地震により被害を受けた建物があると言う情報を得て、調査に赴いた。ラージコートよりさらに約80km程度西に位置し、ブジからも直線で約90kmの距離に位置しており、カッチ湾に面した街である。現地の人の話では全壊・半壊といった大きな被害は無かったようであるが、壁や柱に大きなクラックが入った建物は多数あったようである。車により市街を巡回した際は、それ程目立った被害は無かったが、時々被害を受けた建物も見られた。

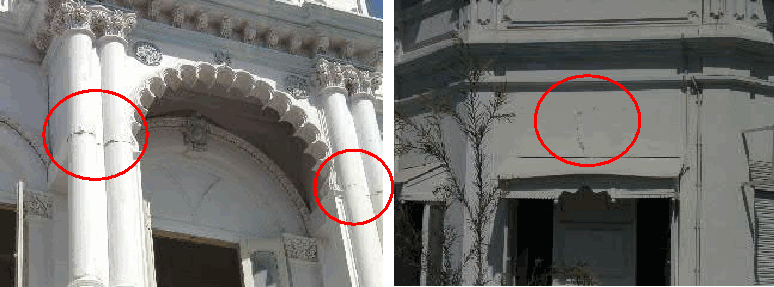
写真5〜7 Hotel aram (P.N.Marg, Jamnagar-361 008.)
植民地時代に建てられた歴史ある建物だそうである。内部には大きなクラックも見られた。
4-4.バチャウ周辺(Bhachau)
ラージコートから国道(?)8Aを進み、マリヤ(Maliya)を過ぎてから長い橋を超えた辺り(バチャウより20km程度手前)から沿道の建物に明らかな地震による被害が見受けられるようになり、バチャウの手前15km辺り(Samakhial)では、全壊、半壊の建物が多く見られた。バチャウの中心部あたりでは、かなりの建物が倒壊したとみられ、それらが瓦礫の山を築いていた。この辺りは昔からの伝統的な構法の住宅(石や日干しれんがを積み、表面を漆くい、モルタルで塗ったもの)などが多数見受けられ、これらの多くが完全に倒壊したものと考えられる。
バチャウでは家を失った住民が多数テント生活をしており、プレファブによる仮設住宅も建設され始めていた。また救援団体が多数入っているようであり、軍のテントなども見られた。

写真8 Samakhial近辺のビル

写真9 Samakhial近辺の住宅

写真10 バチャウ近辺のガソリンスタンド
4-5.ブジ(Bhuj)
今回の地震の震源に近い都市であり、やはり膨大な被害を受けていた。伝統的構法による構造物はかなりのダメージを受けており、全壊しているもの(半壊したものを解体してしまったのかもしれないが)が多数見られた。またRC造のビルなどもかなりダメージを受けており、補修可能なものは少ないと思われる。しかしながら最近に建てられたと思われる戸建住宅(RC造かと思われる)では、それ程のダメージを受けていないものも見られた。
現在も地震の被害の影響は強く残っているものの、ある程度都市機能も回復しつつあるようで、開店している商店や路上の屋台なども見られた。

写真11:KC Polytech LTD(ブジから東10km)


写真12:左 柱の被害, 写真13:右 下部詳細


写真14〜15 ブジ市街の被害状況
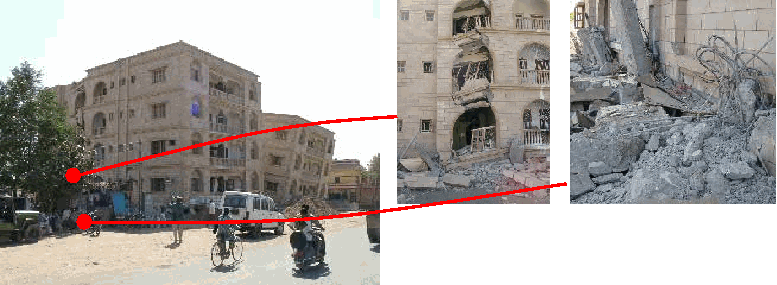
写真16:左 1階ピロティが潰れたビル(ブジ市街)
写真17:中 側面の被害
写真18:右 下部詳細
4-6.アンジャー(Anjar)
ブジや次のガンディダンに比べ小さな町であるが、石やレンガ積みの伝統的構法による構造物が多かったと思われ、被害の程度はひどく、一面それらの瓦礫が積み重なった場所が多々見られた。

写真19 アンジャー市街の瓦礫の山

写真20 左部分が倒壊したマンション
4-7.アディプアー(Adipur)
比較的新しい建物が多く、少し高級な住宅地という感じであった。またそれらの戸建住宅では、外観においては比較的被害が少なかった。 しかし、マンションなどでは倒壊しているものも多数見られた。

写真21 比較的被害が軽微な住宅


4-8.ガンディダン(Gandhidham)
市街には中・高層のビルも多く見られ、それらの被害が数多く見られた。ただしそれらの被害程度にはかなりばらつきがあり、比較的きちんと建てられている建物ではそれ程ダメージを受けていないものも見られた。ブジなどに比べ、かなり生活の復旧が進んでいるようで、開店している商店なども多数見られた。


写真24 半分が倒壊したビル 写真25 1階部分が潰れてしまった病院

写真26 Hotel Sharma Resorts, 写真27 同 倒壊した部分
4-9.ロダイ(Lodai)
ロダイは今回の地震の震源に最も近いと言われており、ブジより北東に約30km離れた位置にある。建物は古い伝統構法によるものがほとんどであり、それらが倒壊した瓦礫の山が一面に見られた。現地の人に、村の奥の平原に地割れがあるとのことで案内してもらい、それらを確認した。またこれらの近辺で、水が湧き出したところも見られた。地割れはそれ程大きなものではなかったが、今回の地震ではその他の場所では地割れを確認しておらず、この辺りに断層が通っているものと考えられた。またここにおいて、出会った救援ボランティアの方から、バチャウに近いチョウバリという村でもこのような地割れがあるという情報を得た。
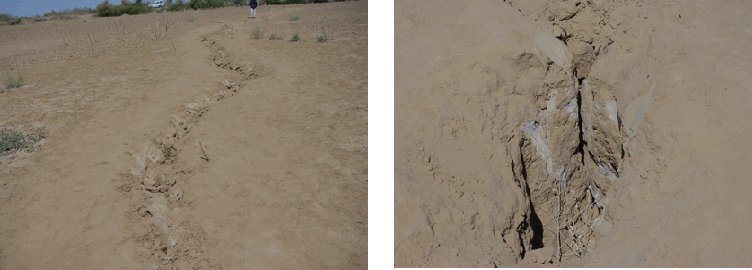
写真28 平原に通った地割れ 写真29 同 詳細

写真30 地割れそばの水が湧き出したところ
4-10.チョバリ(Chobari)
チョバリはバチャウの北約25kmに位置する小さな町である。この辺りも被害は大きく、ロダイ辺りとあまり変わらない程度に思われた。地割れはチョバリの町の中心よりやや手前、バチャウから20km付近のところに道路を横切って東西に通っていた。ここでも地割れの規模は小さく、道路も走行にあまり支障が無い程度の被害であった。

写真31 極端な破壊をしたRCの建物


写真32:左 地割れ
写真33:右 詳細
4-11.被害状況の特徴
今回の地震については膨大な被害が報告されており、また実際に現地を見て回った状況でも、広い範囲にわたって倒壊などの大被害が確認され、その尋常ではない地震の規模が想像された。しかしその一方で、地盤についての被害はほとんど見られず、我々が確認した地割れも規模の小さなものであった。(応用地質社により発見された亀裂についても60〜80cmの高低差であったとのニュースを聞いている。)このためこれらの地域の地盤特性が、今回の地震においてどのように影響したか良く検討する必要があると思われる。
また我々が確認した地割れの位置、さらに応用地質社が確認した地割れの位置(ブジ市から東に約55キロ離れたブダルモラ村の北側)から考えると、今回の地震を引き起こした断層は、ブジからバチャウにかけてのやや北側を東西に走っているものと考えられる。このことはこれに沿った帯状の地域で被害が顕著であることからも想像される。さらに、今回の地震では南北方向、特に南方向に被害が顕著である建物が多く、このような被害特性と断層の方向性の関係などについて今後更なる検討が必要と思われる。
被害を受けた建物に関しては、まず現地の伝統的構法であるというレンガあるいは石を積みその表面をモルタルなどで覆ったものに被害が多かった。これらの構造物は、鉄筋はほとんど用いていないようであり、比較的新しいものでも被害が顕著であった。
RC造のものもかなり被害が見られたが、それらは1階が完全にピロティになっているなどの構造計画的な問題、鉄筋不足や不適切な配筋(特に帯筋)などの部材設計の問題、コンクリートにおいて骨材が容易に抜け出したり付着がほとんど見られないという材料・施工の質の問題、などなど、様々な原因も観察できた。したがって比較的きちんと建てられていると思われる建築物は、被害も比較的軽かった。
我々は個々の建築物について詳細な調査をすることは出来なかったが、今後の調査によりこれらの被害を引き起こした要因が明らかにされることを期待する次第である。
5.おわりに
今回の地震は最初に述べたように、稀にみる大規模な地震ではありましたが、その被害を増大させた要因として、現地の建築構造物における耐震性の不足も否めないと思われます。また被害を受けて危険と思われる建物が未だに利用されているような現状もあり、また余震も続いていると言われています。今後出来るだけ早急に、それらの建築構造物についての安全度を調査するなどの処置も必要かと思われます。
今回の調査にあたり、悲惨な生活を送る現地の人々の中で、訪問者としての後ろめたい気持ちを感じつつも、このような被害を二度と起こさせないためにも、この地震から得たデータを最大限に生かし、今後の被害防止に役立てることが重要であるとも感じた次第であります。
今回の調査は、時間も短く、事前の情報が少なかったため、ともかく現地の方々からの情報を頼りに、行き当たりばったりで被災地を回らざるを得ませんでした。そのため外見的な調査しかできず、いろいろと情報が足りない部分もあります。今後新たに調査に向かわれる研究者の方々により、更に踏み込んだ正確な調査がなされることを期待しております。
また、ここで報告した内容につきましては、まだ十分な解析・検討がなされておりません。そのような不確実な情報であることをお断りすると共に、ご意見、ご指摘、新たなる情報などがございました際には、ご連絡いただければ幸いです。
秋田県立大学
Copyright 2000 AKITA PREFECTURAL UNIVERSITY.
All rights reserved